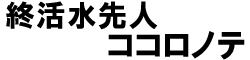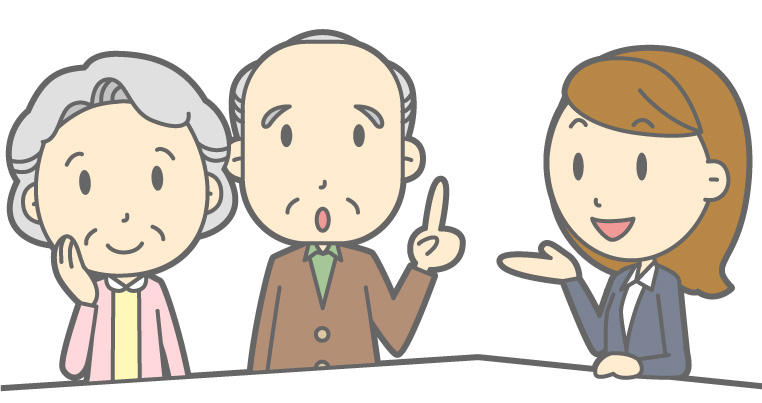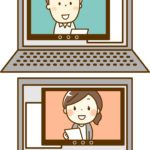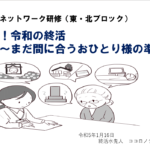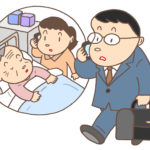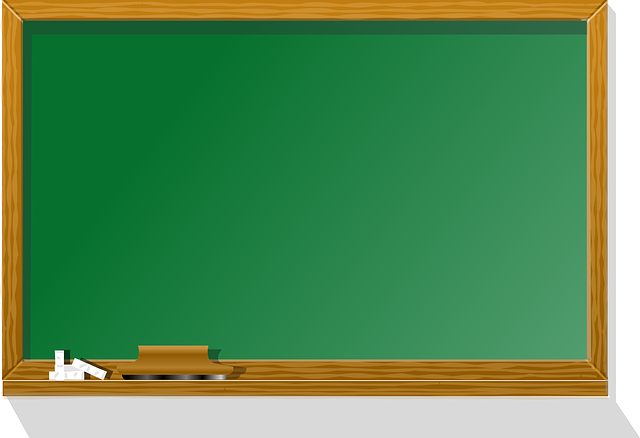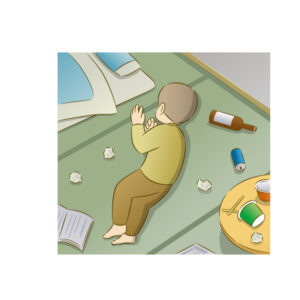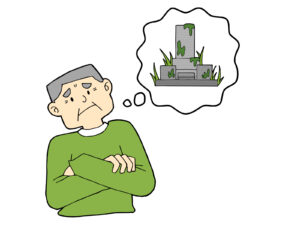突然の病気が見つかった。大ケガをしてしまった。
”まさか、自分がなるなんて”と後悔していませんか。
20代や30代などの若い世代の方や、病気やケガと無縁だった方には、
医療費についての準備や心構えはできていないと思われます。
高額な医療費が請求された場合について知っておくべきこと4つについてまとめました。
終活の専門家、医療資格を持つ終活水先人 ココロノテ 遠藤がご説明いたします。
この記事では以下の事が分かります
保険給付の種類
本人(被保険者)、家族(被扶養者)が病気・ケガ・出産・死亡した時診療費を負担したり、いろいろな給付金を支給します。
| 区分 | 給付の種類 | |
| 病気やケガをしたとき | 被保険証で治療を受けるとき | 療養の給付 入院時食事療養費 入院時生活療養費 保険外併用療養費 訪問看護療養費 |
| 立て替え払いの時 | 療養費 高額療養費 高額介護合算療養費 |
|
| 緊急時に移送されたとき | 移送費 | |
| 療養のために休んだ時 | 傷病手当金 | |
| 出産したとき | 出産育児一時金 出産手当金 |
|
| 死亡した時 | 埋葬料 | |
健康保険を使っても高額な医療費が請求された場合には、立替払いが利用できますので説明いたします。
1、高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)
- 公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、同一月で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額があとで払い戻される制度。(厚生労働省ホームページより)

年齢や収入によって異なります。


- 入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません。
- 高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。(「世帯合算」や「多数回該当」)
世帯合算

多数回該当

申請方法
- ご自分が加入している公的医療保険
(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に
高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。 - 病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
- 申請後、支給までに3カ月程度かかります。
- 高額療養費の支給申請は診察を受けた月の翌月の初日から2年です。2年以内なら過去にさかのぼって支給申請をすることができます。
2、限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)
- 70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示することで、窓口の負担が1カ月の自己負担限度額を払います。
- 支払う医療費を減らすことができて、後から払い戻しを申請する手間が省けます。
- 手術が予定されているような入院では是非「限度額適用認定証」を準備しましょう。
申請方法
- ご自分が加入している公的医療保険
(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に
限度額適用認定申請書を提出または郵送する - 郵送で申しこむ場合は数日かかることもありますので、入院が決まったらすぐに手続きをしましょう。
- 限度額適用認定証が送られてきます。

限度額適用認定証での注意
- 2つ以上の病院に同時にかかっている場合は病院ごとに計算します。
- 同じ病院でも、内科などと歯科がある場合は別に扱います。
- 同じ病院でも通院と入院は別会計です。
- 入院中の食事代や保険がきかない室料・差額ベッド料、歯科の自由診療等は支給の対象外になります。
3、高額医療・高額介護合算制度
(こうがくいりょう・こうがくかいごがっさんせいど)
高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の
医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、自己負担額を軽減する制度です。
申請をすることによって負担額の一部が払い戻されます。
高額介護合算療養費制度の条件と対象
- 国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること
- 1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること
医療保険制度を利用する世帯に、介護保険の受給者がいる場合には、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合、支給の対象となります。
医療機関や調剤薬局の窓口、あるいは介護サービス事業者などに対し、自己負担限度額を超えて支払った場合に、その差額分を2つの方法で支給されることになります。
- 介護保険に係る部分は「高額医療合算介護サービス費」として支給
- 医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として支給
尚、自己負担分ではなく、保険制度が負担する部分の費用負担は、医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて負担します。

高額介護合算療養費制度の対象とならない場合について
<費用>
公的医療:
- 入院時の食事代
- 差額ベッド代
介護保険:
- 自身の要介護区分の支給限度を超えて利用したサービス代
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費の自己負担分
- 施設サービスなどでの食費や滞在費
高額療養費や高額介護サービス費の対象にならない費用は合算制度でも対象外です。
<条件>
- 年間自己負担の限度を超えた額が500円未満の場合
- 公的医療保険と介護保険のどちらか一方のみ自己負担している場合も
- 同一世帯であっても「夫が75歳以上で後期高齢者医療保険,妻が国民健康保険に加入している」など保険制度が異なる場合には合算ができない
などの注意が必要です。
申請方法
<申請先>
加入している公的医療保険の窓口へ申請が必要です。
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険⇒市区町村
- 協会けんぽ、健康保険組合など⇒勤務先
<申請期限>
- 毎年8月1日から2年間
- 被保険者が亡くなってしまった場合は死亡した日の翌日から2年間
<注意事項>
高額介護療養費制度における自己負担限度額を上回りそうな場合、
- 国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人には市区町村から通知が届きます。
- 協会けんぽや健康保険組合などの加入者には通知はされません。
自分で医療費、介護サービス費を計算して自己負担額を上回る可能性があれば勤務先などに確認のうえ申請を行う必要があります。
4、医療費控除 (いりょうひこうじょ)

医療費控除は、確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。
自分以外にも生計を同一にする家族の分もまとめて申告が可能です。
支払った医療費に応じて税金を計算し直す
医療費控除は、支払った医療費の額がそのまま戻ってくると勘違いされやすいのですが、
支払った医療費に応じて税金を計算し直すというものです。
医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。
保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金のほか、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。
治療を目的とした医療行為に支払った費用は、医療費控除の対象となります。
<医療費控除の対象となる医療行為>
- 病院での診療費/治療費/入院費
- 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
- 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
- 通院に必要な交通費
- 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
- 子供の歯列矯正費用
- 治療のためのリハビリ/マッサージ費用
- 介護保険の対象となる介護費用
医療機関で支払う診察代や薬代には、保険外診療のものも含まれています。薬局で購入する風邪薬などの市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。また、入院費用や入院中の食事代も含まれます。妊娠・出産では、定期健診や検査代、出産や入院のための費用、不妊治療費用も対象になります。
歯の治療では、保険適用外の高価な材料を使った場合も含まれます。歯列の矯正では、嚙み合わせを直す目的で子供が施術を受ける場合には適用されます。
医療機関に通院や入院をするための交通費のうち、バスや電車などの公共の交通機関によるものは、医療費控除の対象となります。タクシーの利用は、急を要しているケースや電車やバスの利用ができない場合のみ認められ、申告の際に領収書の添付が必要となります。
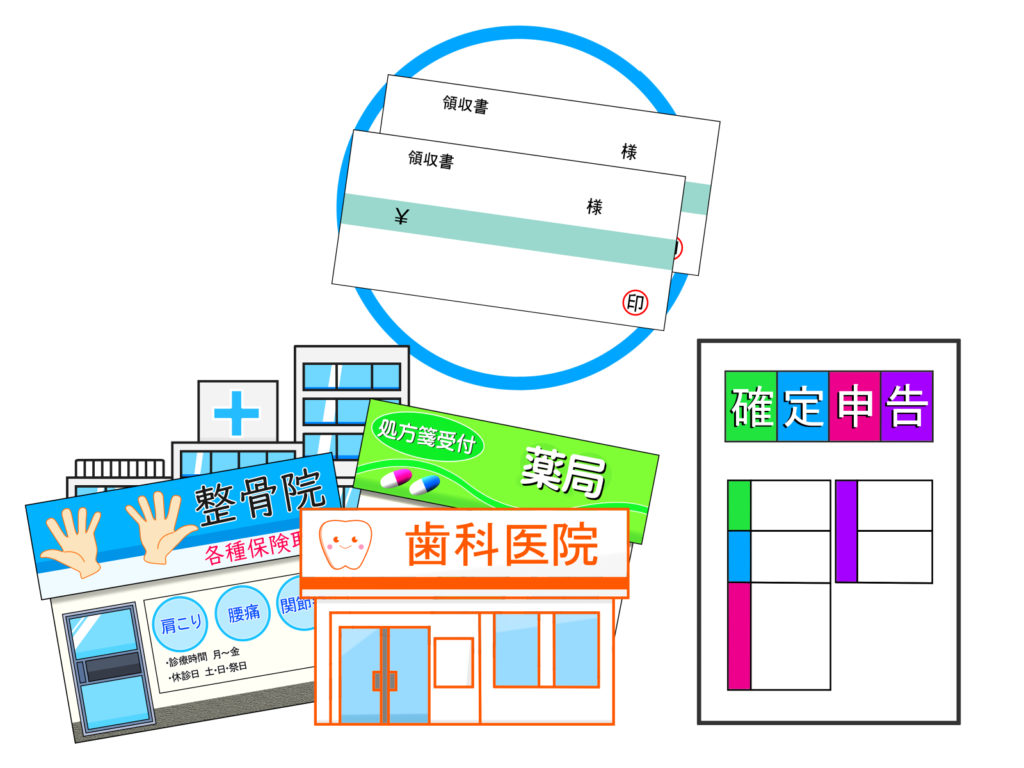
まとめ
知っていると知らないとではかなり違います。
- 高額療養費制度は聞いたことがあるという人でも限度額適用認定制度を知らない人が多いです。
- 手術が予定されている入院では期間を同月内で入退院できるように調整すると良いでしょう。
- 医療費の領収書は家族の分も保管しておきましょう。
- 医療費の3割を用意できるならば先に支払って高額療養費の請求をするでも良いですが、手続きしても3カ月は戻ってきません。厳しいようなら、限度額適用認定証の手続きをしておくことをお勧めします。
相談行くのに不安な方は、終活水先人 ココロノテにご相談ください。